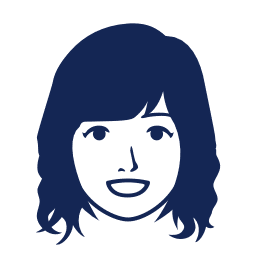「宿題を忘れても自己責任」なんていう声も耳にしますが、ママによる家庭学習での勉強や宿題確認はいつまで必要でしょうか?
わたし自身の教員生活を振り返ると、「宿題確認をしてもらっているかどうかは、内容を見れば一目瞭然」というのが正直な感想です。そしてやはり、宿題をきちんと見てもらっている子どもの方が、学習の定着率も上がります。
そうはいっても、いつまでも付きっきりで家出の勉強や宿題確認をするのはデメリットも大きくなります。今回は、段階に応じた自立のすすめを紹介します。
小学校低学年:なるべく丁寧に勉強の確認
勉強、宿題のやり方はもちろん、えんぴつの持ち方や書くときの姿勢もまだまだ気になる小学校低学年。なるべく丁寧に勉強や宿題の確認を行いましょう。
勉強に対して興味があり、ワクワクドキドキを感じているこの時期に、しっかりと家庭学習の習慣を身につけたいです。
「勉強ができる・できない」もまだ表れにくく、無理なく宿題をこなせる子どもが多いでしょう。小学校低学年では、「丁寧な字が書けているか」「決められた宿題のやり方を守れているか」が確認ポイントです。
隣に付きっきりになることが難しい場合は、家事をしながらときどき様子を見るだけでもかまいません。以前紹介した「リビング学習」もおすすめです。
ここで注意したいのが、「勉強や宿題を見る=問題を完ぺきに仕上げる」ではないということ。
十分丁寧に書けている字を「ちょっと崩れている」と何度も書き直しさせたり、子どもが遊ぶ時間を大幅に削ってまでトコトン机に向かわせたり、現段階でそこまでの必要はありません。
大切なのは、家庭での学習習慣を身につけること。毎日机に向かい、できれば楽しく勉強に取り組めるような環境作りを行いたいものです。
小学校中学年:勉強の最後に確認をしっかりと
中学年になると、勉強や宿題のやり方にも十分慣れ、自分の力だけでできるようになってきます。
また、そろそろ思春期に差し掛かるころ。ずっと付き添ってべったりと勉強の確認をされることに、抵抗を感じ始めるかもしれません。子どもひとりで学習に取り組むようにしましょう。
ところが、ここで勉強や宿題の確認を完全に放り投げてしまうのはダメ。子どもが宿題を終えたら、最後の確認を行ってください。漢字であれば「“留めハネはらい”がきちんと書き分けられているか」、計算であれば「計算が合っているか」はもちろん、「途中式をきちんと残しているか」が確認のポイントとなります。
人は誰だって、「できれば怠けたい」と思うもの。ママのチェックがない子どもの宿題は「雑」「字が汚い」「サボる」「わざと問題を飛ばす」「分からない問題を放置する」など、一目見れば分かります。
逆に、例え勉強が苦手でも、ママにチェックしてもらっている子どもはきちんと宿題をやり遂げてきます。この毎日の積み重ねが、後の学力に大きな差を与えるのです。
付きっきりよりは少し手を離し、最後のチェックはしっかり行う。これが「勉強の自立」への第一歩です。
小学校高学年:勉強・宿題の確認は週1回。質問にはすぐ答える
高学年になったら、最後のチェックも頻度を落としていきます。週に1回~2回「今学校でどんなことを習っているの?」という感じで、さりげなく確認できるのが理想です。
確認のポイントは、「字が雑になっていないか」「間違いが多くないか」です。高学年になると勉強も次第に難しくなりますから、宿題で数問間違えても、それを学校で「直す」ことができれば大丈夫。何問も間違えているようならフォローしましょう。
宿題確認とは別に、子どもから「分からない」と質問があればなるべくすぐ見るようにしてください。分からない問題を分からないまま放置してしまう癖が付くと、後々苦労します。「分からないことはその場で解決」が基本です。
いつまでも勉強や宿題の確認するのではなく、子どもに自立を促す
「宿題確認はいつまでも続けた方が良い」「丁寧に見れば見るほど良い」という熱心なママも増えていますが、必ずしもそれが正しいとは限りません。
極端に言えば、「中学生や高校生になっても、つきっきりで勉強・宿題を教えないとできない」なんていう事態にも。
「ママに見ていてもらわないと宿題ができない」「自分の意志で勉強を始められない」となってしまっては、かえってマイナスです。子どもの段階に応じて、宿題確認も変化させましょう。少しずつ手を離し、子どもの自立を促します。
勉強をやりたがらない子どもにイライラすることがあるかもしれませんが、怒鳴って無理にやらせようとしたり、「宿題をしないならゲームを捨てるよ」などのネガティブな声かけをしたりするのは逆効果。学習環境を整える、スモールステップを設定する、などの方法を試してください。
また、「学校の勉強に付いていけてない」や「宿題だけでは物足りなさそう」と感じる場合には、宿題以外の家庭学習も検討してください。早い段階でつまずきに気付いたり、子どものさらなる力に気付いたりできるのも、宿題確認のメリットです。
▼人気記事
家庭学習の習慣は子どもの一生を支える
以上、ママの勉強、宿題の確認について、段階に応じた自立のすすめを紹介しました。
これが確認のポイントとなります。
子どもが家庭学習の習慣を身につけることができたら、高校受験や大学受験、就職した後の資格試験まで、一生を支える大きな力となります。子どもがなるべくポジティブな気持ちで机に向かえるような働きかけをしたい