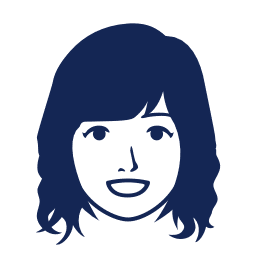二人目育児の難関、上の子の赤ちゃん返り。新生児のお世話で大変なママにとって、上の子のワガママやグズグズが大きなストレスになることも多いでしょう。
実際わたしも、下の子が生まれたときには、上の子の赤ちゃん返りに悩まされました。
赤ちゃん返りはなぜ起きるのでしょうか?どう対応するのがいいのでしょうか?
今回は、赤ちゃん返りの対応法を4つ紹介します。
2人目の「赤ちゃん返り」は悪いこと?
「赤ちゃん返りを防ぎたい」「赤ちゃん返りしないためには?」と考えられることも多いですが、上の子が赤ちゃん返りをするのは当たり前のこと。
上の子は、これまで独り占めできていた周りからの愛情が、赤ちゃんに取られてしまったと感じます。「赤ちゃんは泣いたらすぐに抱っこしてもらえる」「外に出かけても、赤ちゃんばかり話しかけられている」…そんな風に考えてしまうのも仕方ありません。
もちろん、上の子への愛情がなくなったわけではありませんが、下の子のお世話に手がかかるのも事実。さみしい気持ちを完全になくすことは難しいでしょう。
ただ、赤ちゃん返りは、ママが大好きで信頼している証でもあります。「もっとぼく・わたしのことを見てほしい」「かまってほしい」「こんなに大好きなのに」という、子どもなりの愛情表現です。
だから、大切なのは「赤ちゃん返りをさせない」ことではなく、「赤ちゃん返りをどう受け止めるか」ということ。適切な対処法を心がけ、子どもとママで愛情のやり取りをしてください。
「赤ちゃん返りの二人目」の気持ちに寄り添う
赤ちゃん返り中の上の子は、ママが「これから赤ちゃんのお世話をしよう」というタイミングで「〇〇行きたい」「〇〇してほしい」と言い出すもの。
「ちょっと待って」「あとでね」と返してしまいがちですが、単純な後回しは「ママは赤ちゃんの方が大切なんだ」と感じさせてしまうことにつながります。
ここでおすすめの声掛けは、「順番ね」。赤ちゃんだから、お兄ちゃん・お姉ちゃんだから、ということではなく、先にやり始めた方を優先してください。
その代わり、上の子のことをしている間に赤ちゃんが泣きだしても、なるべく上の子を優先する必要があります。
上の子は、好きでお兄ちゃん・お姉ちゃんになったわけではありません。「まだ赤ちゃんでいたい」という上の子の気持ちにも、なるべく寄り添うようにしましょう。
赤ちゃん返り特有の要求にはなるべく応える
赤ちゃん返りをすると、ママがびっくりするような要求をしてくることがあります。
よく聞くのが、「おっぱいを飲みたい」「オムツをはきたい」「赤ちゃんの服を着たい」というもの。我が家の場合は、「哺乳瓶でお茶を飲みたい」と言われました。
このような要求を聞くと、反射的に「これは赤ちゃんのものでしょ」「お兄ちゃん・お姉ちゃんには要らないよ」と返してしまいそうになりますが、ぐっとこらえましょう。
達成可能な要求であれば、なるべくさせてあげることがポイントです。大抵の場合、一度経験することで満足します。何度か繰り返し要求されることもありますが、大人になっても続くなんていうことはありません。
一時的な心の安定として、可能な限り受け入れるようにしてください。
赤ちゃん返りの子と「二人きりの時間」をもつ
お兄ちゃん・お姉ちゃんになったと言っても、まだまだママに甘えたい年ごろ。パパや祖父母に赤ちゃんを預けて、上の子と「二人きりの時間」をもつこともおすすめの対処法です。
短時間でもママを独占することで、上の子もママの愛情をいっぱい感じ、気持ちが安定します。お友だちと遊んだ話や、遊びに行きたい場所の話などをすれば、コミュニケーションをとる良い機会にもなるでしょう。
お出かけが難しい場合は、赤ちゃんが寝ている時間が狙い目です。絵本を読む、お風呂に入るなど、上の子との時間を楽しみましょう。
わたしが取り入れたのは、「秘密のおやつタイム」。下の子が寝ている間に、一緒に飴をなめたり、チョコをひとかけ食べたりしました。
「おいしいね」と微笑み合うだけで、ホッと心が安らぐもの。上の子のためだけでなく、自分にとっても一息つける時間となりました。
赤ちゃん返り中は愛情表現を多めにする
「ママの愛情が取られてしまう」という不安から始まる赤ちゃん返り。
ママからの愛情をたっぷり感じることができれば、少しずつ不安も和らぎます。ぎゅっと抱きしめるのはもちろん、頭をなでる、絵本を読むときには膝に座らせるなど、スキンシップを多めに取るように心がけてください。
「大好きだよ」と言葉でも愛情を伝えることができればベスト。下の子が生まれたからといって、上の子への愛情に変化はないことを伝えましょう。
ママ自身の息抜きも忘れないで
以上、赤ちゃん返りの対応法4つを紹介しました。
二人の育児や日々の家事に加え、赤ちゃん返りの対応は大変なもの。
無理をしすぎてママ自身が心身のバランスを崩してしまうことも少なくありません。無理はしすぎず、ママ自身の息抜きも忘れないようにしてください。
「子どものことがかわいいと思えない」「つい厳しい態度を取りすぎてしまう」などは、心からのSOSかもしれません。周りに助けを求めてください。